2010年11月05日
みよちゃんとの思い出
連日書いている片桐健司氏の講演会に関連して、今日は
ひーままが小学1年生だった時の思い出を書いていきます。
ひーままが公立小学校に入学したのは、今から38年前
入学した初日から、ひーままにはとっても不思議なことがありました。
ひーままのクラスの1年4組だけ、後ろにお母さんが座っていたのです
この方はみよちゃんのお母さんで、みよちゃんの障がいのために
お母さんが毎日、付き添っていたようなのです。
「みよちゃんだけ、ママと一緒でずるいな~!」と思ってみたこともありました
みよちゃんの障がい名は未だに判りません・・・
子供達の間では、「生まれた時は障がいがなくて、注射で障がい児になったから、
ひまわり(特殊学級)じゃない普通クラスにいる」なんて言われていました
ただ、みよちゃんが授業中によく奇声を発していたことは鮮明に覚えていて、
その度にお母さんが「みよ!静かにしない!」と言って、手などを何度も
叩いていたのも鮮明に覚えています。
私がみよちゃんによくされたのは、お下げ髪を思いっ切り引っ張られたこと
その度に、お母さんが「ひーままちゃん、ごめんね・・・ 」と
」と
とても辛そうに何度も謝ってくれたことも覚えています。
確かに、と~っても痛かったけれど、不思議とみよちゃんを恨んだり、
嫌いになったことはなかったです。
給食をお盆毎投げられたこともあって、その時は「ラッキー 」って思ったし
」って思ったし
ひーままは今と違ってその頃は、食が細くて全部食べないといけない
給食の時間が地獄で、地獄で・・・
担任の先生が自分の給食を私の所にもってきてくれたのを見て、
「せっかく、みよちゃんが投げてくれたのに 」とすら思いました
」とすら思いました
みよちゃんと恨んだり嫌いにならなかった理由は、
みよちゃんから多くのことを学んだからだと思います
確かに授業中の奇声で、授業が中断することは度々・・・
でも、小1のひーままは、「なんで、みよちゃんは奇声を発するのかな?」、
「きっと、みよちゃんは何は嫌なことがあるんだろうな・・・」
「何をしてあげたら、みよちゃんは静かになるのかな?」
「自分とみよちゃんは何が違うのかな?」などと
授業そっちのけで一生懸命に考えました
昨日、コメントを下さったみらいさんのお言葉を拝借すると、
「高度な知的興味 」をみよちゃんからもらっていたのです。
」をみよちゃんからもらっていたのです。
ある日の体育の時間、お遊戯かハンカチ落としか何かで、
みよちゃんが円の真ん中になったことがありました。
その時は、みよちゃんは奇声を発しない所かニコニコ笑っていたのです
子供心に、教室の一番後ろのドアの隣の席が嫌なんじゃないかなぁ?
お母さんが後ろに座っているから、その席なんだろうけれど、
真ん中の席にしてあげたら、騒がないんじゃないかなぁ?
と思ったもの記憶しています
でも、親の間から「子供の勉強が遅れる」系のクレームがたくさん
出たようで、みよちゃんの席は真ん中どころか、お母さんの席の隣
(掃除道具入れの前のみんなの席からは隔離感のある所)に移されました
子供心に、奇声が余計パワーアップしたようにも思ったけれど・・・
そして、ある日から、みよちゃんは1年4組に来なくなりました
先生に、「みよちゃんはどうしたんですか?」と聞いた所・・・
「みよちゃんはひまわり学級にいるのよ」と言われて、
朝、下駄箱の所で待っていたら、みよちゃんが養護の先生と
ひまわり学級に入っていく姿を見て、とっても淋しく感じました
みよちゃんがいなくなってから、確かに授業は静かに受けられるように
なったけれど、小1のひーままの心には大きな穴がポッカリと開きました
小1の時には数や文字などたくさんのことを学んだのでしょうが、
ひーままにとって、一番学べたことはみよちゃんを通してのことでした
ひーままが常々書いている「違い好き 」、「自分/自分」、「ONLY ONE」という
」、「自分/自分」、「ONLY ONE」という
感覚はみよちゃんとの関係で築き上げたのではないかと思っています
これらの感覚は、ひーままの礎 となっています。
となっています。
その後、ひまわり学級でも、みよちゃんの姿を見ることはなくなりました。
転校だったのかな・・・
44歳になったみよちゃんはどうしているかな?
会ってみたいなぁ~ そしてお礼を言いたいなぁ~
そしてお礼を言いたいなぁ~
「短い間だったけれど、一緒に過ごせて嬉しかったよ!」って・・・
ご訪問ありがとうございます<m(__)m>
ランキングに参加しているので、下のバナー
をクリックして頂けると励みになります♪
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
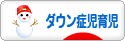
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
ひーままが小学1年生だった時の思い出を書いていきます。
ひーままが公立小学校に入学したのは、今から38年前

入学した初日から、ひーままにはとっても不思議なことがありました。
ひーままのクラスの1年4組だけ、後ろにお母さんが座っていたのです

この方はみよちゃんのお母さんで、みよちゃんの障がいのために
お母さんが毎日、付き添っていたようなのです。
「みよちゃんだけ、ママと一緒でずるいな~!」と思ってみたこともありました

みよちゃんの障がい名は未だに判りません・・・
子供達の間では、「生まれた時は障がいがなくて、注射で障がい児になったから、
ひまわり(特殊学級)じゃない普通クラスにいる」なんて言われていました

ただ、みよちゃんが授業中によく奇声を発していたことは鮮明に覚えていて、
その度にお母さんが「みよ!静かにしない!」と言って、手などを何度も
叩いていたのも鮮明に覚えています。
私がみよちゃんによくされたのは、お下げ髪を思いっ切り引っ張られたこと

その度に、お母さんが「ひーままちゃん、ごめんね・・・
 」と
」ととても辛そうに何度も謝ってくれたことも覚えています。
確かに、と~っても痛かったけれど、不思議とみよちゃんを恨んだり、
嫌いになったことはなかったです。
給食をお盆毎投げられたこともあって、その時は「ラッキー
 」って思ったし
」って思ったし
ひーままは今と違ってその頃は、食が細くて全部食べないといけない
給食の時間が地獄で、地獄で・・・

担任の先生が自分の給食を私の所にもってきてくれたのを見て、
「せっかく、みよちゃんが投げてくれたのに
 」とすら思いました
」とすら思いました
みよちゃんと恨んだり嫌いにならなかった理由は、
みよちゃんから多くのことを学んだからだと思います

確かに授業中の奇声で、授業が中断することは度々・・・
でも、小1のひーままは、「なんで、みよちゃんは奇声を発するのかな?」、
「きっと、みよちゃんは何は嫌なことがあるんだろうな・・・」
「何をしてあげたら、みよちゃんは静かになるのかな?」
「自分とみよちゃんは何が違うのかな?」などと
授業そっちのけで一生懸命に考えました

昨日、コメントを下さったみらいさんのお言葉を拝借すると、
「高度な知的興味
 」をみよちゃんからもらっていたのです。
」をみよちゃんからもらっていたのです。ある日の体育の時間、お遊戯かハンカチ落としか何かで、
みよちゃんが円の真ん中になったことがありました。
その時は、みよちゃんは奇声を発しない所かニコニコ笑っていたのです

子供心に、教室の一番後ろのドアの隣の席が嫌なんじゃないかなぁ?
お母さんが後ろに座っているから、その席なんだろうけれど、
真ん中の席にしてあげたら、騒がないんじゃないかなぁ?
と思ったもの記憶しています

でも、親の間から「子供の勉強が遅れる」系のクレームがたくさん
出たようで、みよちゃんの席は真ん中どころか、お母さんの席の隣
(掃除道具入れの前のみんなの席からは隔離感のある所)に移されました

子供心に、奇声が余計パワーアップしたようにも思ったけれど・・・
そして、ある日から、みよちゃんは1年4組に来なくなりました

先生に、「みよちゃんはどうしたんですか?」と聞いた所・・・
「みよちゃんはひまわり学級にいるのよ」と言われて、
朝、下駄箱の所で待っていたら、みよちゃんが養護の先生と
ひまわり学級に入っていく姿を見て、とっても淋しく感じました

みよちゃんがいなくなってから、確かに授業は静かに受けられるように
なったけれど、小1のひーままの心には大きな穴がポッカリと開きました

小1の時には数や文字などたくさんのことを学んだのでしょうが、
ひーままにとって、一番学べたことはみよちゃんを通してのことでした

ひーままが常々書いている「違い好き
 」、「自分/自分」、「ONLY ONE」という
」、「自分/自分」、「ONLY ONE」という感覚はみよちゃんとの関係で築き上げたのではないかと思っています

これらの感覚は、ひーままの礎
 となっています。
となっています。その後、ひまわり学級でも、みよちゃんの姿を見ることはなくなりました。
転校だったのかな・・・
44歳になったみよちゃんはどうしているかな?
会ってみたいなぁ~
 そしてお礼を言いたいなぁ~
そしてお礼を言いたいなぁ~
「短い間だったけれど、一緒に過ごせて嬉しかったよ!」って・・・
ご訪問ありがとうございます<m(__)m>
ランキングに参加しているので、下のバナー
をクリックして頂けると励みになります♪
↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓
にほんブログ村
Posted by ひーまま (陽満々) at 23:56│Comments(10)
│ひーままのこと
この記事へのコメント
コメントさせて頂きます。
ひーままさんは、とても貴重な体験をすることができたのですね。
非常に羨ましいです。
私も小学校中学年の頃に、同じ学年に障がいのある子がいましたが、クラスが違う上に全校生徒1500人のマンモス校だったので、あまり接点はありませんでした。
でも確かに、私も周りもあまり悪いイメージを抱いていなかった気がします。
私は小学校高学年で韓国にホームステイしたり、逆に我が家にホームステイに来る外国の方がいたりと、中学入りたての最初の席がアルゼンチン出身の子のとなりだったりしたせいか、国境や人種の境目が曖昧な人間に育ちました。
早いうちに、自分と違う人たちと出会うことは、その後の人生にとって非常に重要だと感じます。
年齢が低いうちは、相手の違いが気になっても、それが理由で相手を嫌いになったり差別したりすることはないので、そういう違いがあると別の場所へ行くことになるとこどもが思ってしまうことの方が、かなり危険だと思います。
要は、みんなと一緒じゃないと不安、仲間外れにならないようにしか行動しない人間を生んでしまうんではないかと思うのです。
理想はいくらでも思い浮かぶのですが、現実は厳しく、何か実現可能な考えはないかと思う日々です。
ひーままさんは、とても貴重な体験をすることができたのですね。
非常に羨ましいです。
私も小学校中学年の頃に、同じ学年に障がいのある子がいましたが、クラスが違う上に全校生徒1500人のマンモス校だったので、あまり接点はありませんでした。
でも確かに、私も周りもあまり悪いイメージを抱いていなかった気がします。
私は小学校高学年で韓国にホームステイしたり、逆に我が家にホームステイに来る外国の方がいたりと、中学入りたての最初の席がアルゼンチン出身の子のとなりだったりしたせいか、国境や人種の境目が曖昧な人間に育ちました。
早いうちに、自分と違う人たちと出会うことは、その後の人生にとって非常に重要だと感じます。
年齢が低いうちは、相手の違いが気になっても、それが理由で相手を嫌いになったり差別したりすることはないので、そういう違いがあると別の場所へ行くことになるとこどもが思ってしまうことの方が、かなり危険だと思います。
要は、みんなと一緒じゃないと不安、仲間外れにならないようにしか行動しない人間を生んでしまうんではないかと思うのです。
理想はいくらでも思い浮かぶのですが、現実は厳しく、何か実現可能な考えはないかと思う日々です。
Posted by STH at 2010年11月06日 09:13
再度のコメント失礼します。
ひーままさんはまだお子さんが集団生活を
しておられない年齢ですよね。
うちの子子供と同じクラスの障害のあるお子さんが
暴力を振るうと書きましたが、週に何日かは療育
残りを保育園というダブルスクールです。でも年長ともなれば
かなり高度なこともやるので、できないことにいらだって
暴力を振るうのではないかとの見解もきかれました。
ひーままさんを見ていると何が何でも普通学級と
いう印象を持ちます。ご自分が学校の勉強を軽視される姿勢と
矛盾を感じます。まったく理解できない算数や英語の授業に
だまって座っておとなしくしておけということは
かえってお子さんの心を傷つけ負担を強いると思いますよ。
勉強のできるといわれる子も毎日が必死なんですよ。
そこをご理解いただけませんか。
ひーままさんはまだお子さんが集団生活を
しておられない年齢ですよね。
うちの子子供と同じクラスの障害のあるお子さんが
暴力を振るうと書きましたが、週に何日かは療育
残りを保育園というダブルスクールです。でも年長ともなれば
かなり高度なこともやるので、できないことにいらだって
暴力を振るうのではないかとの見解もきかれました。
ひーままさんを見ていると何が何でも普通学級と
いう印象を持ちます。ご自分が学校の勉強を軽視される姿勢と
矛盾を感じます。まったく理解できない算数や英語の授業に
だまって座っておとなしくしておけということは
かえってお子さんの心を傷つけ負担を強いると思いますよ。
勉強のできるといわれる子も毎日が必死なんですよ。
そこをご理解いただけませんか。
Posted by みらい at 2010年11月06日 09:45
こんばんわ。
みよちゃんとの関わりによって当時のひーままさんの心に芽生えた感情、これこそが障がい児の親の求めるものではないでしょうか!!
幼稚園から小学1年生頃の子供達は、自分と他人の違いには気付いても、いろいろな角度から観察しそれを受容していると思います。
それに対して大人は、偏った見方でそれを排除しようとする心だけが働くのではないかと思います。
小学校では学年に合わせて”命”の授業を受けます。4年生頃では身体の不自由な方を招いて話を聞いたり、地域のバリアフリーについても学習します。
でも、本当に障がいのある人や身体の不自由な人を思いやり理解する心を育てたいのなら、小さい頃からそういう人達と生活を共にする事が最善ではないかと思います。
先日娘の学校で学芸会がありました。学年に混じっての参加でしたが、入場の時やステージに上がる時などに列からはみ出てしまう娘を、前後の子供達がそっと手をつないだり手招きしてくれたりしたおかげで、自分の場所に立つ事が出来ました。
この様な自然なサポートこそが、障がい児の母としては本当に嬉しい事なのです。
この様な子供の思いやりの心は、決して机上の学習で身に付くとは思えません。共に生活する時間があるからこそだと思います。
障がい児、障がい児と言われますが、障がい児とその家族にとっての本当の障がいは、子供の知的面や情緒面などではなく、周りから理解されず排除されるという、目には見えないけれど自分の力だけで乗り超えるには大きすぎる壁が障がいなのです。
そしてこの障がいが無くなったなら、きっと普通学級や支援学級で悩む事も無くなるんだろうなと思います。
みよちゃんとの関わりによって当時のひーままさんの心に芽生えた感情、これこそが障がい児の親の求めるものではないでしょうか!!
幼稚園から小学1年生頃の子供達は、自分と他人の違いには気付いても、いろいろな角度から観察しそれを受容していると思います。
それに対して大人は、偏った見方でそれを排除しようとする心だけが働くのではないかと思います。
小学校では学年に合わせて”命”の授業を受けます。4年生頃では身体の不自由な方を招いて話を聞いたり、地域のバリアフリーについても学習します。
でも、本当に障がいのある人や身体の不自由な人を思いやり理解する心を育てたいのなら、小さい頃からそういう人達と生活を共にする事が最善ではないかと思います。
先日娘の学校で学芸会がありました。学年に混じっての参加でしたが、入場の時やステージに上がる時などに列からはみ出てしまう娘を、前後の子供達がそっと手をつないだり手招きしてくれたりしたおかげで、自分の場所に立つ事が出来ました。
この様な自然なサポートこそが、障がい児の母としては本当に嬉しい事なのです。
この様な子供の思いやりの心は、決して机上の学習で身に付くとは思えません。共に生活する時間があるからこそだと思います。
障がい児、障がい児と言われますが、障がい児とその家族にとっての本当の障がいは、子供の知的面や情緒面などではなく、周りから理解されず排除されるという、目には見えないけれど自分の力だけで乗り超えるには大きすぎる壁が障がいなのです。
そしてこの障がいが無くなったなら、きっと普通学級や支援学級で悩む事も無くなるんだろうなと思います。
Posted by きゅー at 2010年11月06日 23:12
STHさん。
いつもコメントをありがとうございます<m(__)m>
みよちゃんとの思い出、いいでしょ~?
ちょっとだけ自慢しちゃいますね(^^ゞ
この体験を中1の時にしたのではあまり意味がなく、
小1という好奇心旺盛で、偏見などないピュアな心の時に
体験できたのが本当に良かったと思っています。
私の宝物の一つです☆
「早いうちに、自分と違う人たちと出会うことは、その後の人生にとって非常に重要だと感じます。
年齢が低いうちは、相手の違いが気になっても、それが理由で相手を嫌いになったり差別したりすることはないので、そういう違いがあると別の場所へ行くことになるとこどもが思ってしまうことの方が、かなり危険だと思います。
要は、みんなと一緒じゃないと不安、仲間外れにならないようにしか行動しない人間を生んでしまうんではないかと思うのです。」
全くの同感です!!!
おひーさまにも早いうちから、様々な人と交流させようと思っています。
「みんなと一緒じゃないと不安・・・」という気持ちは
何処から生まれるのか常々、気になっていました。
(ひーままには全くないので・・・)
なるほど!!
STHさんの解説で、そのメカニズムの一部が見えて来た気がします!
ちょっとスッキリできました。ありがとうございました<m(__)m>
いつもコメントをありがとうございます<m(__)m>
みよちゃんとの思い出、いいでしょ~?
ちょっとだけ自慢しちゃいますね(^^ゞ
この体験を中1の時にしたのではあまり意味がなく、
小1という好奇心旺盛で、偏見などないピュアな心の時に
体験できたのが本当に良かったと思っています。
私の宝物の一つです☆
「早いうちに、自分と違う人たちと出会うことは、その後の人生にとって非常に重要だと感じます。
年齢が低いうちは、相手の違いが気になっても、それが理由で相手を嫌いになったり差別したりすることはないので、そういう違いがあると別の場所へ行くことになるとこどもが思ってしまうことの方が、かなり危険だと思います。
要は、みんなと一緒じゃないと不安、仲間外れにならないようにしか行動しない人間を生んでしまうんではないかと思うのです。」
全くの同感です!!!
おひーさまにも早いうちから、様々な人と交流させようと思っています。
「みんなと一緒じゃないと不安・・・」という気持ちは
何処から生まれるのか常々、気になっていました。
(ひーままには全くないので・・・)
なるほど!!
STHさんの解説で、そのメカニズムの一部が見えて来た気がします!
ちょっとスッキリできました。ありがとうございました<m(__)m>
Posted by ひーまま at 2010年11月07日 00:41
at 2010年11月07日 00:41
 at 2010年11月07日 00:41
at 2010年11月07日 00:41みらいさん。
再びのコメントをありがとうございます<m(__)m>
ひーままさんはまだお子さんが集団生活を
しておられない年齢ですよね。
→プレ幼稚園と療育センターの通園クラスに週1回ずつ
通わせています。いずれもシステマティックなので、
十分集団生活と理解しております。
でも年長ともなればかなり高度なこともやるので・・・
→みよちゃんは当時小1で、体の大きい子だったので、
みらいさんが書かれているお子さんより更に暴力的
だった可能性があります。でも、私はぜんぜん怖くなかったし、
恨んだり、嫌いになったこともありませんでしたよ♪
できないことにいらだって
暴力を振るうのではないかとの見解もきかれました。
→みよちゃんもそうだったのかな?と今になって思います。
ひーままさんを見ていると何が何でも普通学級と
いう印象を持ちます。ご自分が学校の勉強を軽視される姿勢と
矛盾を感じます。
→どこかで私の就学に対するスタンスを書いていますか?
まだ決めていませんよ!!!
「ひーままは決して普通学級にだけ拘っているのではなく、
おひーさまに合った就学先に就学させたいと思っています。
それが普通学級なのか、支援学級なのか、支援学校なのか
今は分かりませんが、両親が就学先を決めたいと思います。
選択肢がいくつかあって、その中から親が子供に合った
就学先を選ぶのがしかるべき姿だと思っています。」
と「障がい児と普通学級1」の中で書いていますけれど・・・
・教育委員会に「強制的」に決められるのは間違っている!
・ダウン症児の中でも大学を卒業した方もいらっしゃるので、
支援級だけでない選択があってしかるべき!
・私とみよちゃんの例から、障がい児が普通級に入学する
ことも意義がある!
を示したくて娘のためにではなく、社会に対して記事を書いています。
なお、「何か何でも普通学級という印象を持たれる」みらいさんの
邪推がどこから来るのかとても不思議です。
まったく理解できない算数や英語の授業に
だまって座っておとなしくしておけということは
かえってお子さんの心を傷つけ負担を強いると思いますよ。
→「まったく理解できない」と言いきれますか?
障がいによって好きな学科に違いがあったりしますよ。
ダウン症に限って言えば、文字情報は好きらしいので、
英語は意外と好きかもしれません。
現にフランス語学科を卒業した人もいらっしゃるんですよ!
ただ、娘は理解の難しい子かな?と勝手に思っているので、
恐らく「支援級」だと思っているくらいなんですが・・・。
小学校での机上の勉強はあまり重視していないのですが、
机上以外の体験(色々な人との交流など)には
大いに期待しています。
また友人談によると、支援級の授業内容は普通級では
学べないこともあってかなり充実しているようなので、
逆に楽しみにしている位なんですが・・・。
勉強のできるといわれる子も毎日が必死なんですよ。
そこをご理解いただけませんか。
→この一節で何を仰りたいのでしょうか?
前文との関連からかなり飛躍していて、論理的に文章が流れておらず、
理解に苦しんでおります(>_<)
再びのコメントをありがとうございます<m(__)m>
ひーままさんはまだお子さんが集団生活を
しておられない年齢ですよね。
→プレ幼稚園と療育センターの通園クラスに週1回ずつ
通わせています。いずれもシステマティックなので、
十分集団生活と理解しております。
でも年長ともなればかなり高度なこともやるので・・・
→みよちゃんは当時小1で、体の大きい子だったので、
みらいさんが書かれているお子さんより更に暴力的
だった可能性があります。でも、私はぜんぜん怖くなかったし、
恨んだり、嫌いになったこともありませんでしたよ♪
できないことにいらだって
暴力を振るうのではないかとの見解もきかれました。
→みよちゃんもそうだったのかな?と今になって思います。
ひーままさんを見ていると何が何でも普通学級と
いう印象を持ちます。ご自分が学校の勉強を軽視される姿勢と
矛盾を感じます。
→どこかで私の就学に対するスタンスを書いていますか?
まだ決めていませんよ!!!
「ひーままは決して普通学級にだけ拘っているのではなく、
おひーさまに合った就学先に就学させたいと思っています。
それが普通学級なのか、支援学級なのか、支援学校なのか
今は分かりませんが、両親が就学先を決めたいと思います。
選択肢がいくつかあって、その中から親が子供に合った
就学先を選ぶのがしかるべき姿だと思っています。」
と「障がい児と普通学級1」の中で書いていますけれど・・・
・教育委員会に「強制的」に決められるのは間違っている!
・ダウン症児の中でも大学を卒業した方もいらっしゃるので、
支援級だけでない選択があってしかるべき!
・私とみよちゃんの例から、障がい児が普通級に入学する
ことも意義がある!
を示したくて娘のためにではなく、社会に対して記事を書いています。
なお、「何か何でも普通学級という印象を持たれる」みらいさんの
邪推がどこから来るのかとても不思議です。
まったく理解できない算数や英語の授業に
だまって座っておとなしくしておけということは
かえってお子さんの心を傷つけ負担を強いると思いますよ。
→「まったく理解できない」と言いきれますか?
障がいによって好きな学科に違いがあったりしますよ。
ダウン症に限って言えば、文字情報は好きらしいので、
英語は意外と好きかもしれません。
現にフランス語学科を卒業した人もいらっしゃるんですよ!
ただ、娘は理解の難しい子かな?と勝手に思っているので、
恐らく「支援級」だと思っているくらいなんですが・・・。
小学校での机上の勉強はあまり重視していないのですが、
机上以外の体験(色々な人との交流など)には
大いに期待しています。
また友人談によると、支援級の授業内容は普通級では
学べないこともあってかなり充実しているようなので、
逆に楽しみにしている位なんですが・・・。
勉強のできるといわれる子も毎日が必死なんですよ。
そこをご理解いただけませんか。
→この一節で何を仰りたいのでしょうか?
前文との関連からかなり飛躍していて、論理的に文章が流れておらず、
理解に苦しんでおります(>_<)
Posted by ひーまま at 2010年11月07日 01:14
at 2010年11月07日 01:14
 at 2010年11月07日 01:14
at 2010年11月07日 01:14きゅーさん。
いつもコメントをありがとうございます<m(__)m>
「幼稚園から小学1年生頃の子供達は、自分と他人の違いには気付いても、いろいろな角度から観察しそれを受容していると思います。」
→そうなんですね・・・。
私はグッドタイミングで、素晴らしい体験をしていたのですね?
学芸会でお譲さんにお友達がして下さったこと!
こういう体験が互いの人間力を育てていくのだと思います。
正に、共に生活する時間があるからこそ!なのだと思います。
仰る通り、こうした体験は机上ではほぼ不可能でしょう。
私は障がい児の母でなかったとしても、みよちゃんとの
体験から障がい児や外国人など様々な違いを持った人々
との交流を幼いうちからさせることの重要性を主張したはずです。
「周りから理解されず排除されるという、目には見えないけれど
自分の力だけで乗り超えるには大きすぎる壁が障がいなのです。」
→片桐健司氏も同様のことを仰っていました。
私もおぼろげにそう思っていたのですが、
片桐氏のお話で、認識を強固なものにすることができました(^O^)/
この辺りのことも書きたいと思いつつ、他の記事を書いていて・・・
近いうちに「障害者権利条約に関して」というタイトルで記事を
書くと思うので、是非、読んでください<m(__)m>
よろしくお願い致します。
いつもコメントをありがとうございます<m(__)m>
「幼稚園から小学1年生頃の子供達は、自分と他人の違いには気付いても、いろいろな角度から観察しそれを受容していると思います。」
→そうなんですね・・・。
私はグッドタイミングで、素晴らしい体験をしていたのですね?
学芸会でお譲さんにお友達がして下さったこと!
こういう体験が互いの人間力を育てていくのだと思います。
正に、共に生活する時間があるからこそ!なのだと思います。
仰る通り、こうした体験は机上ではほぼ不可能でしょう。
私は障がい児の母でなかったとしても、みよちゃんとの
体験から障がい児や外国人など様々な違いを持った人々
との交流を幼いうちからさせることの重要性を主張したはずです。
「周りから理解されず排除されるという、目には見えないけれど
自分の力だけで乗り超えるには大きすぎる壁が障がいなのです。」
→片桐健司氏も同様のことを仰っていました。
私もおぼろげにそう思っていたのですが、
片桐氏のお話で、認識を強固なものにすることができました(^O^)/
この辺りのことも書きたいと思いつつ、他の記事を書いていて・・・
近いうちに「障害者権利条約に関して」というタイトルで記事を
書くと思うので、是非、読んでください<m(__)m>
よろしくお願い致します。
Posted by ひーまま at 2010年11月07日 01:34
at 2010年11月07日 01:34
 at 2010年11月07日 01:34
at 2010年11月07日 01:34ディベートはお得意ですね。
ダウン症の方で大学を出られたのが稀だから
この方が有名な事例なのでそこにスタンダードを置くのは
逆に現実を直視していないと思います。
自分では違うと仰っると思いますが、健常な子に
障害児がどんなに迷惑行為をしてもご自分のみよちゃんとの
体験がいやでなかったと押し付けているように思います。
もしみよちゃんのご家族の方がこのブログを読まれたら
あるいは勝手にこういうことを書いてと不快に感じるかも
しれません。
これで最後にしますが、もしあなたのお子さんが
健常児なら今とまったく同じ就学に関するお考えですか?
ダウン症の方で大学を出られたのが稀だから
この方が有名な事例なのでそこにスタンダードを置くのは
逆に現実を直視していないと思います。
自分では違うと仰っると思いますが、健常な子に
障害児がどんなに迷惑行為をしてもご自分のみよちゃんとの
体験がいやでなかったと押し付けているように思います。
もしみよちゃんのご家族の方がこのブログを読まれたら
あるいは勝手にこういうことを書いてと不快に感じるかも
しれません。
これで最後にしますが、もしあなたのお子さんが
健常児なら今とまったく同じ就学に関するお考えですか?
Posted by みらい at 2010年11月07日 06:18
素朴な疑問です。
友人がダウン症を含む障害者さんの介護をしていて、話を聞くと、中には大人になっても、トイレのお世話を必要とする人がいるんですよね。
それに女の子だと、いずれは生理の時のお世話も必要になりますよね。
障害者の中には、排泄物を壁に塗りたくったり、人に投げ付けたりすることもあるらしいんですが、そういう人が普通の学校に行く場合、誰が後始末するんでしょうか?
友人がダウン症を含む障害者さんの介護をしていて、話を聞くと、中には大人になっても、トイレのお世話を必要とする人がいるんですよね。
それに女の子だと、いずれは生理の時のお世話も必要になりますよね。
障害者の中には、排泄物を壁に塗りたくったり、人に投げ付けたりすることもあるらしいんですが、そういう人が普通の学校に行く場合、誰が後始末するんでしょうか?
Posted by 亜希 at 2010年11月07日 17:39
みらいさん。
再びコメントをありがとうございます<m(__)m>
ダウン症の方で大学を出られたのが稀だから
この方が有名な事例なのでそこにスタンダードを置くのは
逆に現実を直視していないと思います。
→確かに稀なのかしれません。
だからと言って、子供一人一人の可能性を
スタンダード、マジョリティー、マイノリティー
という数値で測って消すことはできないはずです。
大切なのは障がい児のあるなしに係わらず、子供の可能性を
どう伸ばしていくか、そのために学校や親が何をするのか
ということだと思います。
自分では違うと仰っると思いますが、健常な子に
障害児がどんなに迷惑行為をしてもご自分のみよちゃんとの
体験がいやでなかったと押し付けているように思います。
→受け取り方は人それぞれですので、
押しつけていると取られても仕方ないと思います。
もしみよちゃんのご家族の方がこのブログを読まれたら
あるいは勝手にこういうことを書いてと不快に感じるかも
しれません。
→これは真逆だと思います。
当時のみよちゃんのお母さんは針のむしろ状態で
通学していたように思います。38年経った今でも、
「自分達の選択によって、他のお子さんにご迷惑を
かけたのではないか?」と気にされているとすら思います。
それが、たった一人の生徒でも、「みよちゃんと過せて嬉しかった」
=「お母さん達の選択は正しかった!」、「お陰で私は人間力を
増すことが出来た!」と伝えている訳ですから、悪い気はしないと
思いますよ!
もしあなたのお子さんが
健常児なら今とまったく同じ就学に関するお考えですか?
→もちろんです!
みらいさんがこのコメントを下さる数時間前にきゅーさんに
以下のようなコメントを送っています。
「私は障がい児の母でなかったとしても、みよちゃんとの
体験から障がい児や外国人など様々な違いを持った人々
との交流を幼いうちからさせることの重要性を主張したはずです。」
障がい児の母となって説得力がなくなったのですが、
こうした趣旨のことは娘が生まれる前から言ってきていました。
例えば、おひーさまの上に障がいのない小1のお姉ちゃんがいて、
そのクラスに障がいがゆえに加害行為をする子供がいるとします。
その子のことが問題視され、PTAなどでクレームが出た場合、
間違いなく、その子のクラス替え(特別支援級へ)などしないで、
加配の方を付けて下さるよう提案するか提案書を書きます。
なぜこのようなことをするかというと・・・
その方が自分の子供の成長にお得!だからです\(~o~)/
幼稚園から小学1年生頃の子供達は自分と他人の
違いに気付いて、いろいろな角度から観察しそれを受容
する時期だと思われるので、様々な子供達と交流させたいのです。
学力はあとからでも付けられますが、上記の力は時節を過ぎると
付かなくなる気がするので・・・
「ディベートはお得意ですね」とお褒めのお言葉を頂戴しましたが、
みよちゃんとの関係は、観察力→分析力→論理力→主張力を付ける
一助になったのだと思います。ディベートは学力があっても出来る
ものではありません。
みらいさんはお子さんに学力だけでなく人間力(総合力)を
付けさせたいと思われますか?
もし思われるのなら、加害行動を行う子供との関係を利用
しちゃうのも手ですよ!(笑)
これで最後に!と仰らずに、それからも忌憚ないご意見を
頂けましたら幸いです。
お互いの子供がより良い成長をするために、
日本の教育に関して意見交換が出来たら嬉しいです(^O^)/
再びコメントをありがとうございます<m(__)m>
ダウン症の方で大学を出られたのが稀だから
この方が有名な事例なのでそこにスタンダードを置くのは
逆に現実を直視していないと思います。
→確かに稀なのかしれません。
だからと言って、子供一人一人の可能性を
スタンダード、マジョリティー、マイノリティー
という数値で測って消すことはできないはずです。
大切なのは障がい児のあるなしに係わらず、子供の可能性を
どう伸ばしていくか、そのために学校や親が何をするのか
ということだと思います。
自分では違うと仰っると思いますが、健常な子に
障害児がどんなに迷惑行為をしてもご自分のみよちゃんとの
体験がいやでなかったと押し付けているように思います。
→受け取り方は人それぞれですので、
押しつけていると取られても仕方ないと思います。
もしみよちゃんのご家族の方がこのブログを読まれたら
あるいは勝手にこういうことを書いてと不快に感じるかも
しれません。
→これは真逆だと思います。
当時のみよちゃんのお母さんは針のむしろ状態で
通学していたように思います。38年経った今でも、
「自分達の選択によって、他のお子さんにご迷惑を
かけたのではないか?」と気にされているとすら思います。
それが、たった一人の生徒でも、「みよちゃんと過せて嬉しかった」
=「お母さん達の選択は正しかった!」、「お陰で私は人間力を
増すことが出来た!」と伝えている訳ですから、悪い気はしないと
思いますよ!
もしあなたのお子さんが
健常児なら今とまったく同じ就学に関するお考えですか?
→もちろんです!
みらいさんがこのコメントを下さる数時間前にきゅーさんに
以下のようなコメントを送っています。
「私は障がい児の母でなかったとしても、みよちゃんとの
体験から障がい児や外国人など様々な違いを持った人々
との交流を幼いうちからさせることの重要性を主張したはずです。」
障がい児の母となって説得力がなくなったのですが、
こうした趣旨のことは娘が生まれる前から言ってきていました。
例えば、おひーさまの上に障がいのない小1のお姉ちゃんがいて、
そのクラスに障がいがゆえに加害行為をする子供がいるとします。
その子のことが問題視され、PTAなどでクレームが出た場合、
間違いなく、その子のクラス替え(特別支援級へ)などしないで、
加配の方を付けて下さるよう提案するか提案書を書きます。
なぜこのようなことをするかというと・・・
その方が自分の子供の成長にお得!だからです\(~o~)/
幼稚園から小学1年生頃の子供達は自分と他人の
違いに気付いて、いろいろな角度から観察しそれを受容
する時期だと思われるので、様々な子供達と交流させたいのです。
学力はあとからでも付けられますが、上記の力は時節を過ぎると
付かなくなる気がするので・・・
「ディベートはお得意ですね」とお褒めのお言葉を頂戴しましたが、
みよちゃんとの関係は、観察力→分析力→論理力→主張力を付ける
一助になったのだと思います。ディベートは学力があっても出来る
ものではありません。
みらいさんはお子さんに学力だけでなく人間力(総合力)を
付けさせたいと思われますか?
もし思われるのなら、加害行動を行う子供との関係を利用
しちゃうのも手ですよ!(笑)
これで最後に!と仰らずに、それからも忌憚ないご意見を
頂けましたら幸いです。
お互いの子供がより良い成長をするために、
日本の教育に関して意見交換が出来たら嬉しいです(^O^)/
Posted by ひーまま at 2010年11月08日 01:04
亜希さん。
ご質問ありがとうございます。
娘は未だ1歳6カ月なので、現状は分かりません。
特別支援学級の先生をしていた友人がいるので
具体的なことを訊いてからの回答とさせて頂きたい
と思います。
回答が得られ次第、この記事のコメント覧に記載します。
しばらくお待ちください!
ご質問ありがとうございます。
娘は未だ1歳6カ月なので、現状は分かりません。
特別支援学級の先生をしていた友人がいるので
具体的なことを訊いてからの回答とさせて頂きたい
と思います。
回答が得られ次第、この記事のコメント覧に記載します。
しばらくお待ちください!
Posted by ひーまま at 2010年11月08日 01:09
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。









